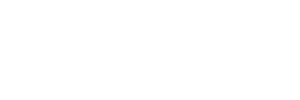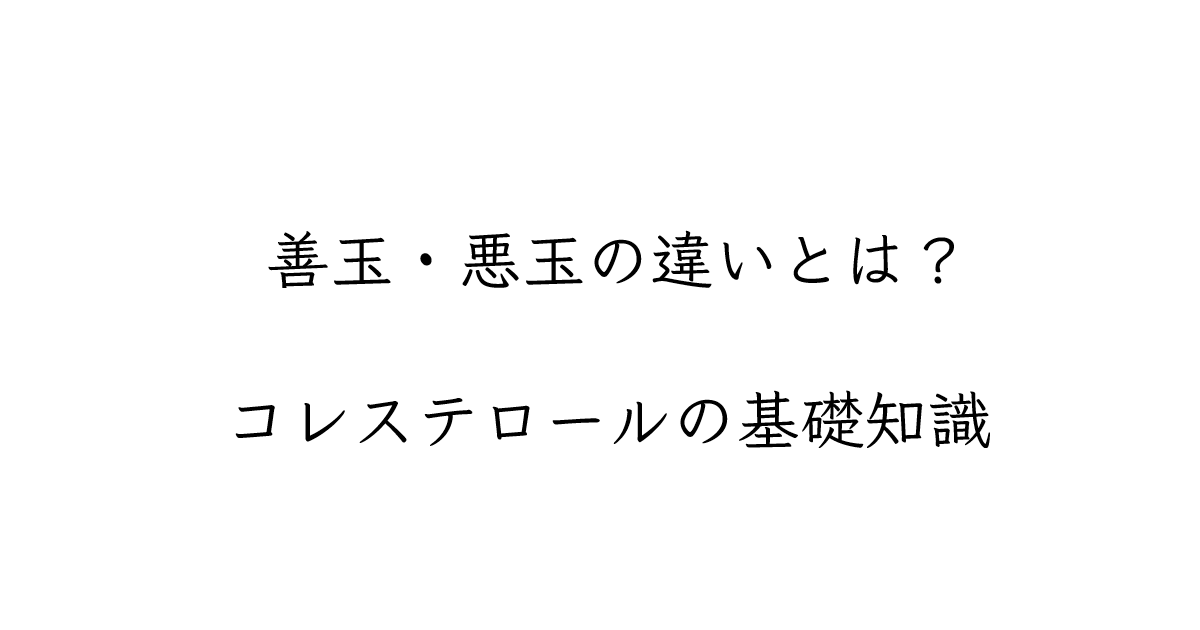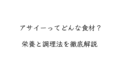コレステロールとは?
コレステロールとは脂質(脂肪)の一種で、人間の体にとって重要な役割を担っています。
細胞膜の構成要素として存在し、ホルモンや胆汁酸、ビタミンDの生成にも必要不可欠な物質です。
体内のコレステロールの約7~8割は肝臓で作られ、残りは食事から摂取されます。
しかし、この「大切な脂質」も、量やバランスが崩れると健康に悪影響をもたらします。
そこで重要なのが、善玉(HDL)と悪玉(LDL)の違いです。
善玉コレステロール(HDL)とは?
善玉コレステロール(HDL: High-Density Lipoprotein)は、血管に付着した余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す役割を果たします。
いわば「掃除屋」のような存在で、血管をきれいに保ち、動脈硬化を防ぐ重要な役割を担っています。
HDLコレステロールが多いと、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを下げるとされており、健康診断でも重要な指標とされています。
悪玉コレステロール(LDL)とは?
一方の悪玉コレステロール(LDL: Low-Density Lipoprotein)は、肝臓で作られたコレステロールを血液を通じて体の各細胞に運ぶ役割を持ちます。
それ自体が悪いというわけではなく、必要な脂質を届ける重要な働きを担っています。
ただし、LDLが過剰になると血管壁に蓄積され、動脈硬化を引き起こす原因となります。これが「悪玉」と呼ばれる所以です。
HDLとLDLの理想的なバランスとは?
一般的には、以下の数値が目安とされています(※基準値は施設や年齢などによって若干異なります)。
- HDLコレステロール
40mg/dL 以上が望ましい - LDLコレステロール
120mg/dL 未満が望ましい - 総コレステロール
200mg/dL 未満が理想的
HDLが少なく、LDLが多いというバランスの悪さは、動脈硬化のリスクを高める要因です。
コレステロールが引き起こす疾患リスク
コレステロール値が長期間高い状態が続くと、以下のような疾患のリスクが高まります:
とくに無症状のまま進行することが多く、「サイレントキラー」とも呼ばれています。
コレステロールを適切に管理するには?
食生活の見直し
- 動物性脂肪の摂りすぎを控える
- 野菜、海藻、豆類など水溶性食物繊維を積極的に摂る
- 青魚(EPA・DHAが豊富)を週2〜3回は食べたい
適度な運動習慣
- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)を週に150分以上
- 筋トレもHDLを増やす効果があるとされています
禁煙・節酒
- 喫煙はHDLを低下させ、LDLを酸化させるリスクが高まります
- アルコールは適量であればHDLを上げることもありますが、過剰摂取は逆効果です
ストレス管理
- ストレス過多はホルモンバランスを乱し、コレステロール値に影響を与えることもあります
定期的な健康診断
- 年に一度は血液検査を受け、自身の状態を把握しましょう
よくある誤解 卵はコレステロールの敵?
かつて「卵はコレステロールが高いから控えた方がいい」と言われていましたが、現在では「食事から摂取するコレステロールは、血中コレステロールに大きな影響を与えない」という見解が主流になっています。
むしろ、卵は良質なタンパク質源であり、適量(1日1〜2個程度)であれば問題がないといわれています。
まとめ
善玉コレステロールと悪玉コレステロールは、どちらも体に必要な存在ですが、その「バランス」が健康維持において極めて重要です。
食生活や運動習慣、ストレス管理など、日々の積み重ねによって数値は改善可能です。